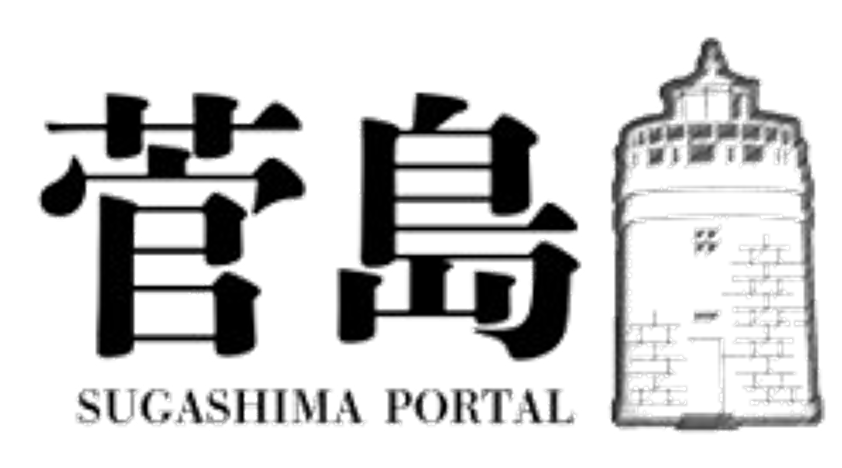菅島は地域行事が盛んです。行事ごとに島民同士が協力し、島を盛り上げています。

春 ~町民運動会・慰霊祭~
春は出会いと別れの季節。
また主要産業の漁業もゴールデンウィークまで皆多忙を極めていますが、中旬を過ぎるとようやく落ち着きを見せてきます。
そんな一息ついたタイミングで行われるのが町民運動会。

小学生、保育所の子供たち、老人倶楽部、青壮年部、婦人会などなど、島民参加で開かれます。
小学校と保育所の運動会も兼ねているため、メインはもちろん小学生や保育所の子供たちなのですが、

「子供たちは島の子であり、島の宝」ですから、みんな応援に熱が入ります。
また運動会に先立って行われるのが、「航空自衛隊慰霊祭」です。
実は菅島、昭和58年(1983年)4月19日、航空自衛隊の飛行機が菅島の大山に墜落し、14名が殉職された歴史があります。
大山には今も慰霊碑があり、毎年4月19日前後に慰霊祭が行われています。

慰霊碑は、ハイキングコースの道中にあります。
夏 ~しろんご祭・天王祭・盆行事~
夏は菅島三大祭り(しろんご祭・天王祭・弓祭り)の2つが開催され、島は大いに盛り上がります。
最初に行われるのがしろんご祭で、毎年7月の第一土曜日あたりに行われます。
しろんごまつりは海女さんのお祭りで、海女さんの海の安全と豊漁を願い、しろんご浜にて祭事が行われます。

宮司による祈祷が済むと、海女さんらは鮑を捕りに海に向かいます。

この海女漁で一番大きいつがい鮑を獲った人が、この年の海女頭となります。
また一番大きな鮑は「奉納海女」によって、しろんご神社にお供えされます。

この鮑は、神事が終わると参拝客に直会としてふるまわれますので、鮑目当てで毎年しろんご祭に来られている人もいるそうですよ。
それからしろんご祭りの日は、海上保安庁の協力によって、菅島灯台の一般公開も行われます。

菅島灯台に入れるのは、年に一度、しろんご祭りの日だけですので、灯台に興味のある方は是非このチャンスをお見逃しなく!!!
そして、しろんご祭りの翌週に行われるのが天王祭。
天王祭は、学園祭に近いのりで、老若男女各種団体による余興が行われます。



会場は菅島アリーナ(菅島小学校体育館)。誰でも入場無料で楽しむことができますので、是非このタイミングで菅島に遊びにきてください。
そして天王祭が終わると、少しずつ盆の準備が始まっていきます。
菅島の盆は細かくやることが決まっている風習が沢山ありますが、中でも目を引くのが笹舟流しです。


島民は笹舟を作り、それを海に流し、ご先祖様をお迎えします。
島に帰ってきたご先祖様は、お盆期間中島で安らぎの時間を楽しみ、「送り船」に乗り、あの世に戻って行かれます。


秋 ~島っ子ガイド・ちびっこ釣り大会・魚食体験・山の神・敬老会~
菅島の秋は、子供たちのイベントが目白押し!
中でも一番大きい行事は、全国的に有名な島っ子ガイドでしょう。



子供たち自ら菅島を調べ、自分の言葉でガイドをしていく取組で、教科書にも載っている有名イベントです。
愛らしい子供たちのガイドに、参加者の大人たちはメロメロで、毎年参加を希望されるリピーター様も数多くいる子供たち主導の人気イベントです。
「魚食体験」は島外の大人たちが羨ましくて仕方がなくなる食材目白押しのイベントです。



魚食体験は、伊勢海老や太刀魚などの食材を子供たちが裁き、島のお母さん&お父さんが調理し、参加者に海の幸が振る舞われます。
主なメニューは、伊勢海老蒸し、太刀魚の天ぷら、伊勢海老&サワラの刺身、アカモクのお浸し、伊勢海老出汁の味噌汁など。
とっても豪華なメニューに参加した大人たちも大興奮のイベントです。
「ちびっこ釣り大会」は島の子供たちが釣りった魚の大きさや重さを競うイベントです。



釣大会後は、みんなでカレーライス。

とっても楽しい時間です。
さらに通過儀礼とも言える「山の神」も、子供たちの大事なお仕事です。


山の神は子供たちが島の各家を回り、各家の無病息災を願い「○○さんぎゃーフイクイセイ」と唱え、祭りの寄付金集めを行います。
山の神の祭事の本番の日は、子供たちが菅島神社の境内に集まり、参拝者の無病息災を再度祈ります。
冬~合社祭、船祝い、弓祭り~
菅島のお正月は、豊漁を願う大漁旗で港が埋め尽くされます。

そして、年が明けると弓祭りの準備が着々と始まります。
弓祭りはしろんご祭りと対照的に男性のお祭りなので、ほとんどの事が女人禁制で行われ、さらに丁寧な禊もします。
とても神聖なお祭りです。






弓子たちが放つ矢の当たり具合によって、今年が豊漁かどうかが決まると言われており、島民はみな弓子の矢がしっかりと的に当たるのを願って、祭りを見守ります。